ANTiQの家とは
代表野口の想いー
「60年先も、好きでいられる家を。」
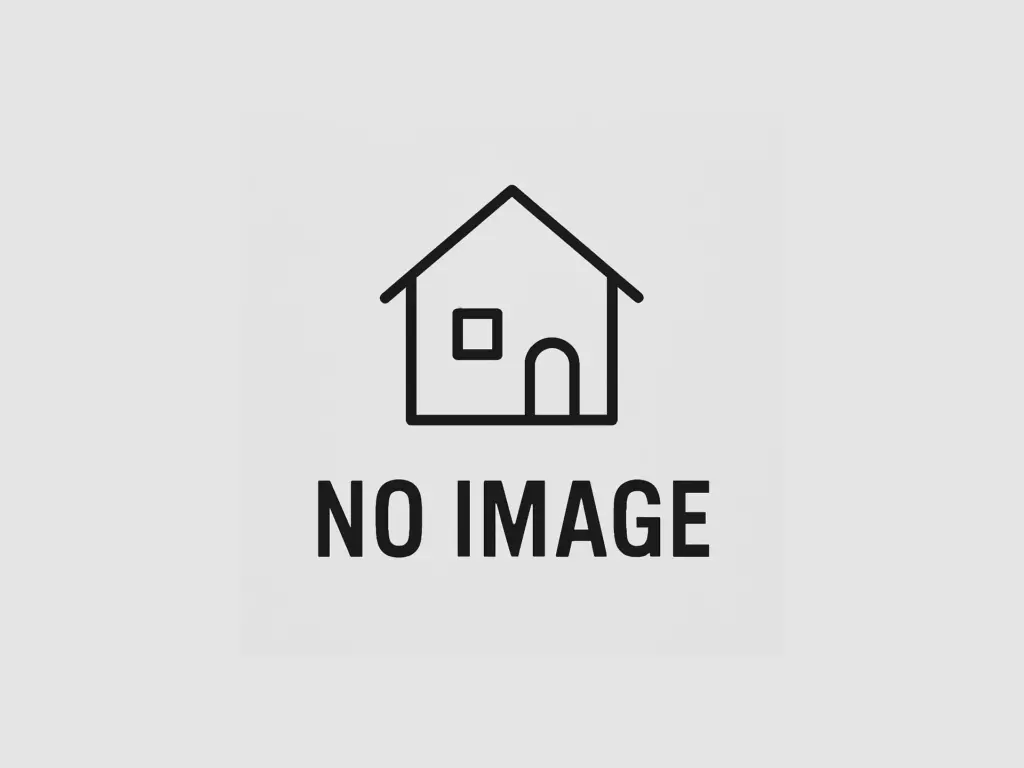
何千万もする家なのに、流行りやデザインやブームで飽きてしまう。そんなの、なんか違うと思うんです。変わらない価値というのは、流行の外側にあるんです。
10年、20年、そして60年先。
そのときも「この家が好きだな」と思えていたら、それがいちばんの理想です。
新しいだけのものは、そこから劣化が始まります。でも本当にいいものは、使い込むほどに味が出て、傷さえもその家の歴史になる。
僕はそういう“育つ家”が好きなんです。
家は完成した瞬間がゴールじゃない。そこから少しずつ育っていくもの。
だからANTiQは、60年後も変わらず住めるように、デザインだけでなく、構造や性能までも長持ちするよう考えています。
外見の美しさも、中身の強さも。
どちらか一方ではなく、どちらも時間に耐えられるように。
僕たちは、その変化を楽しめる人に、ANTiQの家を届けたい。
南仏×日本。代表野口が行きついた、ANTiQの誕生秘話はnoteに掲載しています。
[ #3 ANTiQの原点となる家 →]※note記事
構造と暮らし、
デザインは3番目
見えない場所にこそ、美しさが宿る。

家づくりで本当に大切なのは見えない部分。地震に耐える骨組み、断熱や防寒の性能、暮らしを支える使い勝手。ANTiQの家は”デザイン重視”と思われがちですが、実際は違います。私たちは、まず構造や性能を最優先に次に家事動線などの使いやすさを。デザインはそのあとに考える「3番目」なのです。
1, 見えないけれど、何より大事な「構造」

いくら見た目が素敵でも、地震で崩れるような家では意味がない。
だからANTiQではまず、最新の耐震構造と断熱性能を土台にしています。
見えないところをしっかりつくることで、
見える部分が引き立つと私たちは知っているからです。
2, 使い勝手と機能、そして暮らしの心地よさを

間取りや収納、家事動線、「便利そう」に見えるより、実際に「ストレスがない」ことの方がずっと大切。
・キッチンから洗濯までの動線
・水回りの掃除のしやすさ
・家族の気配を感じながら過ごせる空間
これらは、
暮らしに“ちょうどいいリズム”を与える工夫。
時間が経つほどに「この家でよかったな」と感じてもらえるはずです。
そして、その心地よさを60年先まで保つために。漆喰や無垢材などの“本物の素材”にもこだわっています。毎日の暮らしに触れる場所だからこそ、素材の質感や温もりが大切。歳月とともに味わいを増す”こだわりの建材“が快適さと長持ちを支えています。
3, デザインは、最後に整える“仕上げ”

デザインは大切です。
でも、それは構造と暮らしの土台が
しっかりしているからこそ映えるもの。
・壁の仕上げ、塗りの風合い
・窓の高さと光の入り方
・家具や建具との調和
これらは、
「住む人の物語を引き立てる背景」であって、
“見せ場”ではなく、“暮らしを包む器”なのです。
時を重ねて深まる、
量産では生まれない「表情」

ANTiQの家は、「引き渡しの日」が一番きれいな家ではありません。
木や漆喰、鉄や石が日々の暮らしのなかで風合いを変え、少しずつ味わいを増していきます。
小さな傷や色の変化さえも、そこに暮らした時間の証。
ドアの取っ手にふと触れる瞬間、朝陽が差し込む窓辺の壁、子供がおもちゃを走らせた床の跡。
そうした積み重ねが自然に溶け合い、その家だけの物語が刻まれていきます。
それは単なるエイジングやデザインではなく、
生きた素材と、住む人の手によって完成していく家です。
量産の建材や既製品には、
便利さや機能美があるかもしれません。
けれどANTiQが大切にしているのは、
「どこにもない、唯一無二の」家であること。
ANTiQが目指しているのは、
住むほどに味わいが増していく“素朴な家”。
その想いを、
代表・野口博史がnoteでお話ししています。
[ #2 ANTiQのアンティークになる家→ ]※note記事